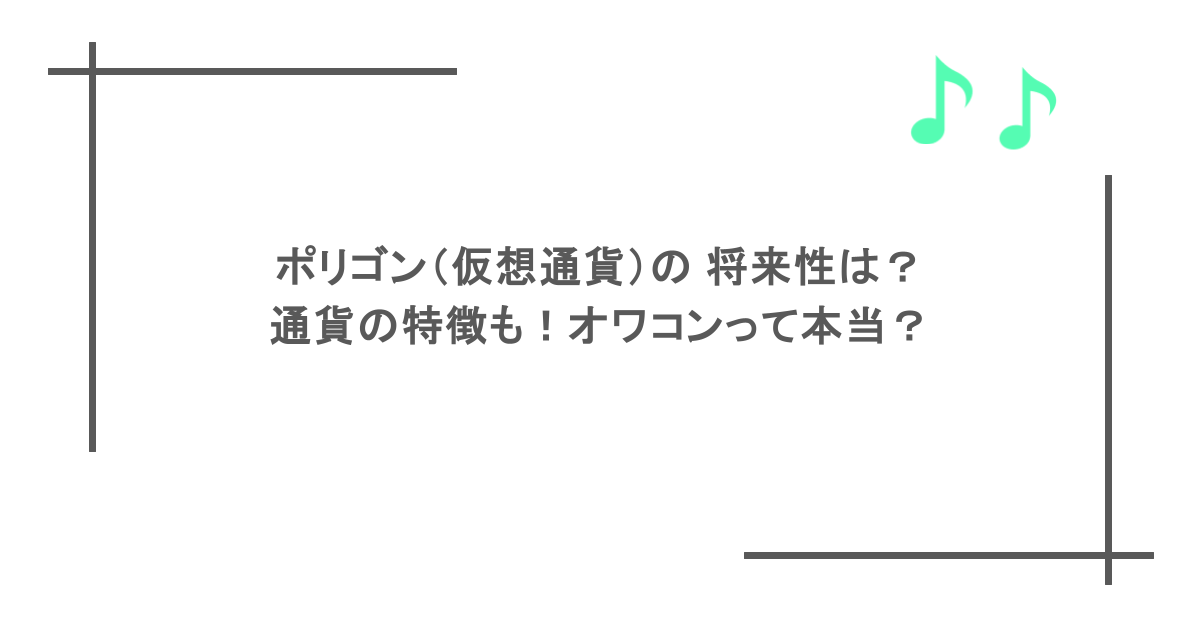最近もポリゴンは注目されているのでしょうか?ポリゴン仮想通貨の将来性というキーワードをSNSやニュースサイトでよく目にするようになりました。2021年あたりに盛り上がりましたが、今は「オワコン」「使われてない」なんて声も聞こえてきます。
当時、仮想通貨ウォレットを使ってNFTやDeFiに触れていた人なら、ポリゴンが「速くて安い」と話題だったのを覚えているのではないでしょうか。実際、同時期には仮想通貨 1000倍になった銘柄も登場し、市場全体が熱狂のピークを迎えていました。ポリゴンもその流れの中で一気に注目を集めたプロジェクトの一つです。本当にオワコンなのか、それともまだまだチャンスがあるのか?ここでは、ポリゴン仮想通貨の基本情報や特徴をわかりやすく整理しながら、将来性を冷静に見ていきたいと思います。
~もくじ~
ポリゴンとは?
ポリゴン(Polygon)は、「Matic Network」という名前で知られていましたが、2021年にリブランディングされて今のポリゴン(MATIC)へと進化しました。暗号資産の中でもサポーター的存在であり、イーサリアムの課題を解決するために作られたプロジェクトです。特に、トランザクション手数料と処理速度という点に注目し、それをサイドチェーンという仕組みでカバーしています。つまり、イーサリアムと同じ土俵に立つライバルではなく、「裏方として支える存在」がポリゴンのユニークなポイントでもあります。
ポリゴンの基本情報
ここで、ポリゴン仮想通貨の将来性を語るうえで欠かせない、基本的なデータも押さえておきましょう。
| 仮想通貨名 | ポリゴン |
| ティッカーシンボル | MATIC |
| 開発開始 / リクライニング | 2017年 / 2021年 |
| コンセンサスアルゴリズム | Proof of Stake(PoS) |
| 発行上限 | 100億 |
| 価格(※2025年10月9日現在) | 約 $0.22 〜 $0.24 |
| 時価総額(※) | 約 4–5億ドル規模 |
| 時価総額ランキング(※) | 44位前後 |
ポリゴンの特徴
ポリゴンの強みは、単に「速い・安い」だけではありません。以下に、主な特徴をまとめてみました。
高速かつ安価なトランザクション処理
イーサリアム本体では、1秒間に15件程度しか取引処理ができません。一方ポリゴンは、1秒間に最大65,000件以上の取引処理が可能。しかもガス代が数円程度と非常に安いです。
セキュリティはPoSで担保
ポリゴンはProof of Stake(PoS)を採用しており、環境にも優しく、バリデーターによってセキュリティも保たれています。これはイーサリアム2.0と同じ仕組み。
幅広いプロジェクトとの連携
UniswapやOpenSeaといった人気dAppsがポリゴンに対応済み。NFT、DeFi、GameFiなど、さまざまなジャンルで使われています。
独自のゼロ知識証明(zkEVM)技術
2023年に登場したPolygon zkEVMは、イーサリアム互換のスマートコントラクトを使いつつ、さらにトランザクションを圧縮して効率化できる技術。これが将来的なカギになるかもしれません。
ポリゴンはオワコンなのか?
SNSや掲示板で「ポリゴンはもうオワコン」と言われている理由には、以下のような背景があります。
トークン価格の下落
2021年のピーク時には約320円まで上がっていたMATICですが、2025年7月で約93円〜109円を推移しています(※CoinGeckoより)。この下落幅の大きさから「終わった」と判断する人も多いようです。
競合プロジェクトの台頭
ArbitrumやOptimismなどのレイヤー2スケーリングソリューションが次々登場しており、ポリゴンのポジションが相対的に薄まってきたという声もあります。
ゼロ知識証明の発展は期待ほどではない?
先ほど紹介したPolygon zkEVMも、期待は高かったものの、現時点でそこまで爆発的な採用例は多くありません。技術は優れていても、実用化や認知には時間がかかるようです。
とはいえ、これらはどれも一面的な見方。価格や話題性だけでオワコンと判断するのは早すぎるかもしれません。
ポリゴン仮想通貨の将来性と期待されるポイント
それでは、ポリゴン仮想通貨の将来性という観点から、今後どうなっていくのか考えてみましょう。
イーサリアムとの強力な連携が継続
ポリゴンとは切っても切れないイーサリアム。今後イーサリアムがさらに広がれば、ポリゴンの需要も連動して伸びる可能性は大いにあります。
Web3企業や大手との提携が進む
2022年にはMeta(旧Facebook)やNike、Starbucksとの提携も報じられました。こうした実用レベルでの採用が続けば、長期的な信頼も高まるでしょう。
技術開発のスピードと多様性
ポリゴンは「zkRollups」「Plonky2」「Miden」など、複数の技術アプローチを同時並行で進めています。失敗してもリカバリーが可能という柔軟さも、プロジェクトとしての強さのひとつです。
まとめ
ポリゴンの将来性について、一時的な価格の下落や話題の沈静化があったものの、本質的な価値や開発力は今も健在ということがわかりました。
確かに、短期的に爆発的なリターンは見込めないかもしれません。でも、イーサリアムの発展とともに、ポリゴンの役割が改めて評価されるタイミングはきっと来るでしょう。
仮想通貨の世界では、表面の情報だけでなく長期的な視点での本質的価値を見抜くことが重要です。今後もポリゴンの動向には要チェックですね。最近では「仮想通貨」をテーマにした漫画作品も登場し、デジタル資産やNFT、Web3の世界を物語として描く動きが広がっています。難しく感じがちなブロックチェーンの仕組みも、『俺物語』のような読みやすい漫画と同じでストーリーを通して理解できるようになっており、エンタメとテクノロジーの融合が進んでいるのです。